【移植医療】欧米と日本、移植コーディネーターの背景を知る

こんにちは、ちびパパナースマンです。
さっそくですが、この記事の信頼性を担保するものを簡単に下記に示します。
- 看護師歴:15年
- 認定レシピエント移植コーディネーター歴:5年以上(専従)
こんな感じで毎日精進していますので、それなりに信頼性はあるかなぁと思います。
▶︎さて今回はですね、移植コーディネーターの背景についてお話していきたいと思います\( ˆoˆ )/
▶︎なぜ背景のお話をするのかと言いますと、何事においても現在を語るには、歴史や背景を知ることから始め、そこから今の矛盾や未来への活眼を磨いていくことが大切だと考えるからです。
▶︎温故知新の精神です。
▶︎まずは、僕たち日本人の移植コーディネーターの背景のお話に入るまえに、欧米でのコーディネーターの背景についてお話ししていきます。
1.世界の移植コーディネーター
1)米国のクリニカルコーディネーター
(1)背景
✅移植コーディネーターは、移植医療の進んだ米国で自然発生的に生まれた専門職であります。
✅当初は、移植コーディネーターという名称もなく、煩雑な移植医療の事務仕事を一手に引き受け、人手不足を穴埋めするような形で始まったとされています。
✅移植医療が発展し始めた1980年代は、看護教育が4年生大学化した時代でもあり、ちょうど臨床現場で看護の専門性が問われるようになってきた時代でした。
✅看護の様々な分野で、Clinical Nurse Specialist(CNS=臨床看護専門家)が活動にあわせて、看護の専門職として認知されるようになりました。
✅そのため米国では、「臨床の」と言う意味の「クリニカル」という言葉を用いたことから、以降、「クリニカル移植コーディネーター」という名称が用いられています。
(一方、日本でいうドナーコーディネーターは、「プロキュアメント移植コーディネーター」と呼ばれています。)
✅以前は、クリティカル移植コーディネーターは、一人あたり200人から300人ほどのレシピエントを担当し、移植前から移植後までケアをしていました。
✅最近では、様々なクリニカル移植コーディネーターが存在し機能別に活動している施設が多いです。
✅症例数の多い施設では、データー管理だけを担うデータ管理移植コーディネーターや生体部分肝移植を行っている施設では、生体ドナー移植コーディネーターを設置しています。
う、うらやましい・・・・(心の声洩れた)
(2)認定制度
✅クリニカル移植コーディネーターは、アメリカ独自の認定組織であるAmerican board for Transplant Certification(ABTC)により認定を受けています。
✅この認定は更新が必要になります。
✅各移植施設は、この認定を受けたクリニカル移植コーディネーターを雇用するように各州から指導をうけています。
✅アメリカでは、クリニカル移植コーディネーターの認定を受ければ「雇用」が保証されることになります。
日本はまだまだ遅れてるなぁ・・・(ここでまた心の声が....)
2)ヨーロッパ諸国のクリニカル移植コーディネーター
(1)背景
✅ヨーロッパでも米国と同じように、ドナー移植コーディネーターは「プロキュアメント移植コーディネーター」と呼ばれています。
✅レシピエント移植コーディネーターも「クリニカル移植コーディネーター」と呼ばれています。
✅ヨーロッパで移植コーディネーターとして活動しているうちの70%以上が、ドナー移植コーディネーターであり、そのうち約10%がドナー移植コーディネーターとクリニカル移植コーディネーターの両方を担っています。
✅そして約5%のコーディネーターが、クリニカル移植コーディネーターとして活動しています。
(2)教育制度
✅移植コーディネーターの研修教育としては、ほとんどの国(50%以上)が、スペインで開発されたかなり集中的な教育プログラム、「Transplants Procurement Management(TPM)」を基盤としていました。
✅またヨーロッパの中でも、英国のレシピエント移植コーディネーターは少し事情が異なっております。
✅移植施設でクリニカル移植コーディネーターが活動していますが、2004年のNurse Managementという雑誌によると、National Health Service(NHS)の指導で、看護の中で特に4つの専門領域で「移植コンサルタントナース」という専門職が設置されました。
✅その4つの専門看護領域とは、『心臓病患者看護』『救急看護』『膿疱性線維症患者看護』『移植患者看護』です。
✅この移植コンサルタントナースは、レシピエント術前から術後まで継続してケアを施し、そのベットサイドでリーダーシップをとって直接的看護にあたる役割を担います。

2.日本のレシピエント移植コーディネーター
背景
✅レシピエント移植コーディネーターの活動が本格的に始動したのは、1989年から始まった生体部分肝移植の件数が急増した1990年代の終わり頃でした。
✅まずは、京都大学、信州大学、北海道大学、北里大学、慶應義塾大学などの肝移植施設で、米国と同様に看護師資格を持つレシピエントコーディネーターが活動し始めました。
✅以後、1999年に日本で初めての脳死移植が行われてから、大阪大学、東北大学、岡山大学などの心臓移植施設や肺移植施設でも設置されるようになりました。
✅日本移植コーディネーター協議会(Japan transplant Coordinators Organization JATCO)は、日本における臓器移植の進歩普及に寄与することを目的とし、ドナー移植コーディネーター・レシピエント移植コーディネーター・院内コーディネーターが共存・相互理解を深めながら、移植コーディネーターとしての学術・研究・教育研修などを行う唯一の団体です。
⬜️日本の認定制度の詳細は、また別の機会に記事にしますm(_ _)m
✅いかがだったでしょうか?何かご自身が思ってた移植コーディネーター像と違うところはあったでしょうか?
✅何れにせよ、どんなふうにでも、何かを感じてくれたら幸いです!
✅良い印象、悪い印象、その他...。"無関心"から"ほんの少しの関心"へと気持ちが動いてくれることを願って止みません。
(注:ブログの情報は最新のものと相違があるかもしれませんこと、ご了承ください。)
潜在看護師の背景や現状についての記事はこちらです。
僕の好きなサッカーの話題で最後はほっこりしてください(^^)
さらに、欧米の話につながりますが、こちらのページでようーロッパサッカーのお話が詳しく書かれています。
ぜひ、リラックスのお供としてご視聴ください!
\最初の1ヶ月 ¥0/
【論文】腎移植レシピエントにおける自己管理の課題と支援の必要性

こんにちは、ちびパパナースマンです。
さっそくですが、この記事の信頼性を担保するものを簡単に下記に示します。
- 看護師歴:15年
- 認定レシピエント移植コーディネーター歴:5年以上(専従)
こんな感じで毎日精進していますので、それなりに信頼性はあるかなぁと思います。
⬜️僕自身の研究テーマのひとつをお伝えします。
研究テーマ:『移植臓器長期生着のための自己管理行動継続への具体的な支援策を見い出す』....(ちょっと改変してますが)
Clinical Question(日頃からの疑問・・・)
自己管理行動が継続できない要因として、レシピエント(患者さん)にばかりその責任を押し付けるような対策(これを"指導"と勘違いしてるコーディネーターや看護師が多い)ばかり作るんじゃなく、もう少し内側...僕たち医療者側に何か責任があって、出来ることがあるんじゃないかなぁって思い続け、Research Questionへと落とし込み研究を進めています。
(補足)
レシピエント➡️臓器や骨髄をもらう者
ドナー➡️臓器や骨髄を提供する者
なぜいきなり自分アピールのような研究テーマの話をしたかと言いますと....
今回はですね、レシピエントとなってから長期になると誰でも訪れるであろう自己管理行動実施程度の低下(定期的な通院や服薬アドヒアランス、感染予防、身体的・心理的・社会環境的側面から考える様々な自己管理行動)について、自己管理行動の継続が出来る/出来ないは患者自身だけの問題ではない!ってのを示してくれた論文を紹介したかったからです。
論文紹介のまえに、まずは自己管理行動継続に関しての過去の論文をチョチョっとどうぞ...。
▶︎腎移植は他の腎代替療法と比べて心血管合併症の発生率が低く、高い生活の質(QOL)をもたらす治療法である。
▶︎近年、腎移植レシピエントにおける移植腎の短期的な生着率や生存率は向上してい
る。
▶︎しかし、ノンアドヒアランスなど非免疫要因による移植腎障害により長期生着には難渋していることから、今後は長期生着の成績を向上させることが課題である。
▶︎移植臓器の長期生着のためには、定期的な通院や服薬アドヒアランス、拒絶反応や感染予防対策、身体的・心理的・社会環境的側面から日常生活における自己管理を網羅的、継続的に行うことが有用である。
▶︎一方で、腎移植後経過期間の長期化に伴い自己管理行動の実施程度が低下していることが明らかにされている。
✅上記までは明らかにされているが・・・
⬇️
▶︎移植医療における自己管理行動全般の実態調査はあるが、レシピエントの長期的な自己管理行動継続には何が必要なのかについての検討は移植領域の文献では見当たらなかった。
✅そこでさらにキーワードを絞って深く検索すると・・・
⬇︎
▶︎精神科看護学の文献より、患者満足度調査により医療の見直しを行い続け、患者の求める医療に近づけることで満足度向上に繋げ、患者-医療者間の意思疎通を図っていくこと。そうすることが、患者自身が「主体的に」自己管理行動の継続へ向かう動機づけになるという報告がありました。
⬇︎
⬜️ここから僕は、「ほらやっぱり〜〜。オラの仮説が立証できるかもしれへんや〜ん!」って自己陶酔しながら研究を進めてた矢先に、今回の論文に出会いましたので共有しようと思いましたとさ...m(_ _)m
というわけで、論文をざっくりと紹介します。
Self-management challenges and support needs among kidney transplant recipients: A qualitative study.
✅今回の論文:腎移植後レシピエントの自己管理と支援についての課題報告。
✅2018年、オランダの研究者らによって報告されました
以下、論文紹介と解釈です。
目的
✅自己管理の課題を検討し、レシピエントが経験したニーズをサポートする。
背景
✅レシピエントは自己管理において積極的な役割を果たすことが期待されている。しかし看護師は、自己管理の継続支援に難渋している。
✅レシピエントが日常に取り入れるためのツールばかりでなく、看護師の視点にたったより深い洞察力に焦点をあてることで、看護師主導の自己管理支援の妥当性と有効性を見い出セル可能性がある。
方法
✅対象は、オランダの大学病院で治療を受けた腎臓移植レシピエント41人により実施された。内容分析にはDCA解析を使用した。
結果
✅移植後の課題には、専門家になること、日常生活の活動を調整すること、医療計画に対処すること、看護師との関係を築くこと、社会的影響に対処することとされた。
✅これらの課題に対処できるようにするために、対象者は疾患特有の知識と指導を受け、他の患者と個人的な経験を共有したいと考えていました。
✅医療だけでなく、感情的、社会的問題についても、看護師と共有し、話し合い、積極的なフィードバックを通して励まされたいと思っっていました。
✅看護師らの教育は、彼らのニーズを満たすのに不十分であると考えられていました。
結論
✅移植後、レシピエントは医学的、感情的、そして社会的課題を扱う上で様々な課題を経験していました。
✅看護師からの現在の支援は、レシピエントたちの感情的および社会的支援のニーズを見落としていました。
✅看護師は、レシピエントの自己管理支援のニーズを満たすことができるようにするために適切なトレーニングが必要とされた。

✅自己管理の継続ができない理由は、レシピエントとその環境だけが問題ではなく、我々移植コーディネーターや看護師の関わり方にも問題がある。
✅僕たちの関わり方や声のかけ方、口調や声のトーン、表情や目線など、それらも全て含めてプロとしての患者さんへの対応の仕方を改善することによって、自己管理行動継続の一助になる。
✅自己管理の中で重要な食事管理。小児移植だけでなくどんなレシピエントにも野菜不足の傾向がある。野菜不足を補うための1つの手段としてはサプリメントも選択肢に入る(※ただし主治医の承諾は必ず得ること)。
野菜不足による食事バランスの崩れや、飲みやすくアレルゲンが少ない安全面が認められている「こどもフルーツ青汁」をオススメする。
詳しくはこどもフルーツ青汁の効果を解説!野菜不足の食物アレルギーっ子より | 家族リフティングの記事に書かれていますのでぜひ読んでみてくださいね。
⬜️こちらも合わせて読んでみてくださいm(_ _)m
【ブランクナースの復帰】看護師転職サイト使わない方がいいの?|潜在看護師の復職応援団
ママさんナースの看護と子育ての両立についての課題や支援の必要性(活用できる国の制度) などについての記事はこちら。
看護師と子育ての両立を目指して〜働き方と活用できる制度まとめ〜|潜在看護師の復職応援団
『移植医療』の歴史を語ろう【その2】

こんにちは、ちびパパナースマンです。
さっそくですが、この記事の信頼性を担保するものを簡単に下記に示します。
- 看護師歴:15年
- 認定レシピエント移植コーディネーター歴:5年以上(専従)
こんな感じで毎日精進していますので、それなりに信頼性はあるかなぁと思います。
今回は『移植医療』の歴史を語ろう【その2】です
なぜ移植医療の歴史について語るのか
・温故知新。
・これからも、移植医療についてたくさんの記事を書いていく者としては、やっぱりできる限り早期に歴史について語っておかないと先へ進めないなぁ〜と思っています。
・ていうか、先に進んでいったとしても歴史が語られていなければ、それはなんだか薄っぺらい情報に繋がるとも思ったからです。
・それに、移植医療従事者でも目の前に必死で、じっくり歴史に関して勉強する人は少ないと思います(これはアカン)。
・僕たちでもそうなのに、日常で移植医療と関わることのない方々に向かって、『臓器提供意思表示カード』の普及ばかり伝えてるような印象が強いのはアカンと思うからです。
・もちろん、「あんまり興味もないし『移植医療の歴史』に関する書物なんて読む気ないわ〜〜」ってのは当然です。
・ですので、需要が少ないことは承知のうえです!( ˆoˆ )/
・だけど、いつかどこかで『移植医療』の歴史をパッと知りたいと考えた時に(そんな時あるのか?とか言わない言わない...笑)、簡単に書かれた資料ってあまりないんですよねぇ〜。
・だったら僕がってことで、ここに超簡単に記そうと思いましたm(_ _)m
(今後、追加修正していく可能性の高い記事になると思います。)
・それから歴史においてはですねぇ、やや表現がきつい部分もありますので、そういったところは歴史を歪ませない範囲で、優しい表現を用いながらお伝えしていこうと思います。
2回目は、
世界保健機構(WHO)と移植医療倫理についてです
WHOと移植医療倫理
・1991年のWHOガイドラインにより、世界的に臓器移植が法制化され、倫理規定としては、"お亡くなりになられた方からの移植">"生体間移植"の方向性が明確化されました。
・しかし米国におけるPaired Organ(いわゆるスワッピング色スワッピング移植)が、生体間腎移植の半数を超えるまでになり、さらに欧州でも採用されることとなり、2007年には公的にPaired Organによる生体肝移植が開始されました。
・皮肉なことに、HLAをマッチさせるシステム上、お亡くなりになられた方からの腎移植や家族間での生体移植より平均でも良い成績であるとのレジストリーも発表され、 WHOでの方向性も影が薄くなっていきました。
・しかし、健康な人にメスを入れ、1つの腎臓を摘出することのリスクも考慮されなければならず、本来はお亡くなりになられた方からの腎移植の増加に向けてのさらなる努力を推し進めなければならないのは事実であり、2007年3月にジュネーブで開催された、Global Concern On Transplantation会議(WHO主催)でも、お亡くなりになられた方からの移植の推進が明文化されました。
・この頃フィリピンでの新たな動きとして、政府公認の財団が、フィリピン人の腎臓を買い上げて、公的に移植する方法を検討しており、このことに関してWHO,ならびに国際移植学会(TTS)も公式に非難声明をだしました。
・1991年のWHOガイドラインでは、生体移植は、Generically related(遺伝的血縁関係)としていましたが、発行間もなく、夫婦間での移植も認めるべきという意見が多く出されました。
・1993年には、Emotionally related(精神的縁者)で実施すべき、としたことから非血縁者間の移植が広がり、欧米のPaired organや、果ては、国が認める臓器の売り買いへと発展を遂げてしまいました(涙)。
・また、WHOマニラ会議(2005年11月)(WHO,WPRO)において、中国厚生省の黄副部長が移植関連では初めて出席し議長を務めましたがその際に、中国では死刑囚ドナーを臓器移植に用いていることを公式に認め、会議でも非難の声があがりました(涙)。
・翌年の2006年には、臓器移植法を整備し、死刑囚からのインフォームドコンセントを得たうえでの臓器提供を合法化するとともに、外国人への移植を禁止することとなりました。
・また、移植の実施できる医療機関を認定施設とし、さらに移植医も認定を受けた者のみ実施できるとされていましたが、新法ではその認定が地方自治体の権限とされたことにより、国際的な不透明感はより一層増す結果となってしまいました(涙)。
・ガイドライン改訂作業に積極的に公式メンバーとして参加した国際移植学会(TTS)では、各国の状況把握や、これらの国々の移植学会との連携で積極的な働きかけを行うことで、公正な移植医療の推進を行ってきました。
・TTSでも、アムステルダム会議、バンクーバー会議を経て、その集大成として、2008年4月30日〜5月2日にかけて、トルコのイスタンブールで、”International Summit on Organ Tourism”を開催しました。世界78ヶ国、154名のメンバーが参加し、3日間の協議の末に『イスタンブール宣言』を取りまとめるに至りました。
★『イスタンブール宣言』(よかったら少し調べてみてください m(_ _)m )
・また、WHOでは2006年より、加盟国の移植医療情報や体制、法制化に至るデータベースを、スペインのONTと共同で作り上げました。(下記リンク先参照下さい)
・わが国でも、日本移植学会国際関連委員会が厚生労働省と協力して、全ての移植医療に係るデータをWHOに供給する体制をとっています。
・しかし、近年の細胞・組織の国際的なシェアリングや、再生医療や細胞治療といったこれまでの「移植医療」とは異なった概念の移植が増加する中、WHOとしては、あくまでご提供された細胞・組織・臓器をヒトに移植するという共通概念上、その安全性をどのように担保するべきかを、WHO移植課(2004年設置)が主体となって、世界各地で会議を開催し検討を重ねてきました。
・その結果、米国では米国組織バンク協会(AATB)、アメリカ・アイバンク協会(EBAA)、アメリカ血液バンク協会(AABB)が、欧州ではEU、並びにECが積極的に参加し、全ての細胞・組織を国際コード化する方向で検討を始めました。
・日本からは、臓器の売り買いなどの出所不明な臓器を無くすという倫理上の理由から、臓器にもWHO国際コードを普及させるべきであるとの提案を行い、EC、TTSがこれに賛同する動きを見せました。
・2009年には、WHO国際シェアーコードの具体的なツールとして、ISO,若しくは、ISBT128の運用に向けての国際的な会議が開催され、このような動きが、単に安全性、トレーサビリティーといった実務的な機能により、リアルタイムでの情報収集も可能となり、ドナー数増加に向けた各国の取り組みも数値化されるため、一層の自助努力が必要となりました。
終わりに
2005年にWHOがジュネーブでESOTとの共同主催で開催した「世界移植デー」(World day for Organ Donation and Transplantation)を共同開催しました。
・2007年には第3回をクウェートで開催、そして、2008年には日本移植学会との共同開催で、第4回世界移植デーが大阪で開催されました。法改正も含めて日本の移植医療が大きく様変わりをする時期に、WHOの国際大会が日本で開催されたということは、その意義は極めて大きいものであります。
・この大会では、WHOや海外からの演者も、日本において脳死問題が臓器提供と並列で議論されている点についての疑問が投げかけられました。臨床的に脳死を人の死として国民が認知し、移植医療を推進するためには、医学としての議論が不可欠であり、海外の経験などからも人の死を認知した後にのみ臓器提供が行われることを、医学から徹底して国民の理解を得るべきであるという指摘がありました。

【超重要!】
日本では『イスタンブール宣言』を受けて、「臓器移植法の改正が必要ダァーーー!!」って議論が高まって、
平成21年(2009)に15歳未満の臓器提供を認める改正法が成立、平成22年(2010)7月に施行されました。
私見(まとめ)

以上、今回はWHOと移植医療倫理の観点から、サクサクっと歴史をまとめました〜😊
▶︎本来、私見を混ぜるつもりはなかったんですが、2点だけ語っちゃいま〜す (笑)
- 「臨床的に脳死を人の死として国民が認知し、移植医療を推進するためには、医学としての議論が不可欠であり、海外の経験などからも人の死を認知した後にのみ臓器提供が行われることを、医学から徹底して国民の理解を得るべきであるという指摘がありました。」とWHOや海外演者たちから投げかけられた件に関しては、もちろん医学的見地から方向性を固める必要があることは理解できますが、全てが一方向での体制になってしまうのは危険だと考えます。国民一人ひとりに、臓器提供に関する『4つの権利』があるように、我々移植医療従事者にも、evidenceをもった多方向の考え方があり、その上で議論を進めていくことが大切であると考えます。
- 臓器移植法が改正され、2010年7月17日に施行されてはいますが、わが国の抱える移植医療の問題は山積みであり、今後並々の改革が必要であることは、移植医療従事者、とりわけ移植コーディネーターであれば身に染みて感じていることは容易に想像できます。この解決策や改善策を考える際には、国際的な見地から我が国の将来像を模索し続けることも必要ではないかと考えています。
★みなさんなら、どのようにお考えになるでしょうか?・・・・・
※あわせてこちらも読んでみて下さいねm(_ _)m
新人看護師のみなさんへ。不安を煽るような言動は見聞きするなよ〜!

こんにちは、ちびパパナースマンです。
さっそくですが、この記事の信頼性を担保するものを簡単に下記に示します。
- 看護師歴:15年
- 認定レシピエント移植コーディネーター歴:5年以上(専従)
こんな感じで毎日精進しています。よろしくお願いしますm(_ _)m
第108回看護師国家試験に合格されたみなさん、おめでとうございます!
残念ながら不合格となったみなさん、必ずこれを大事な経験にしてください。
みなさんは、たくさんの苦労とたくさんの仲間に支えられて今があると思います。
先日、僕はブログで、ここから入職までの期間を遊びだけに費やさないことが大切ですよってお話をしました。
なぜなら今この期間こそ、この先、一生あるかないかの自分自身への大きな大きな投資期間になると考えるからです。
この時期に自分自身の内側へ種を蒔き、毎日毎日コツコツ水やりをし、大きな収穫を得てください。
さて今回のテーマです。
新人看護師のみなさんへ。不安を煽るような言動は見聞きするなよ〜!
まずは、現役看護師(と思われる)みなさんへ
たくさんの希望と多くの不安を抱えているであろう、これから新人看護師となるみなさんに対し、「つらいぞ」「苦しいぞ」「ほとんど辞めていく」など、数え上げたキリがないほどネガティブな表現を浴びせるのやめろ〜〜〜〜。
先輩なら、何か伝えたいんなら、『看護の楽しさ』を存分に伝えてあげるべきでしょう。そうすることでもしかすると、ツラいことも楽しさでカバーできるかもしれないじゃないですか。それが言えないんだったら、黙っときましょう。
これほどまでに、余計なお世話はないと思いますよ(プンプン)。
そして、新人看護師のみなさんへ

どうかクソみたいな先輩(と思われる)人たちのただの主観を、あなたの心の中のバケツに溜めないようにしてくださいね。
唯一、このようなネガティブな表現で不安を煽ることから学べることといえば、「看護の世界は主観だらけの世界」ってことを知れたことです(笑)。
これを肝に命じておけば、冷静な判断・対応ができる確率が上がりますので大丈夫です。
(入職後の配属先で看護記録を見たら、主観だらけでビックリすると思います 笑)
話が少しそれましたが、純粋な気持ちになっているであろうこの時期に、まだ今は空っぽで純粋な心のバケツに、ネガティブな言葉や不安な表現を、どうか溜め込まないようにしてください。
心の中のバケツに溜めていく言葉や経験、喜怒哀楽などはすべて、自分自身で感じ、自分自身で決めていくことが大切です。
なぜなら、あなたたちは”プロ”の看護師だからです。
患者さんやご家族のために、ともに切磋琢磨しましょうね!
そして、看護を楽しみましょう!!!
ぜひ、こちらの記事も合わせて読んでみてください!いつかあなたの役に立つ時がくることを願います。
関連記事:看護師・潜在看護師の離職理由を深掘りする|潜在看護師の復職応援団
新人看護師のあなたに知っておいてほしい記事 ↓
不安や焦りに苛まれないように、自分をいたわりましょうね。
看護師経験豊富な潜在看護師さんでさえ復職への不安は大きいです。
新人看護師のみなさんも不安になることたくさんあるでしょうが、楽観的に楽しく看護をやり続けましょうね!
いざって時は看護師転職サイトを活用して、転職・復職を考えよう!
『移植医療』の歴史を語ろう【その1】

こんにちは、ちびパパナースマンです。
さっそくですが、この記事の信頼性を担保するものを簡単に下記に示します。
- 看護師歴:15年
- 認定レシピエント移植コーディネーター歴:5年以上(専従)
こんな感じで毎日精進していますので、それなりに信頼性はあるかなぁと思います。
さて今回は、
『移植医療』の歴史を語ろう【その1】です
なぜ移植医療の歴史について語るのか
・温故知新。
・これからも、移植医療についてたくさんの記事を書いていく者としては、やっぱりできる限り早期に歴史について語っておかないと先へ進めないなぁ〜と思っています。
・ていうか、先に進んでいったとしても歴史が語られていなければ、それはなんだか薄っぺらい情報に繋がるとも思ったからです。
・それに、移植医療従事者でも目の前に必死で、じっくり歴史に関して勉強する人は少ないと思います(これはアカン)。
・僕たちでもそうなのに、日常で移植医療と関わることのない方々に向かって、『臓器提供意思表示カード』の普及ばかり伝えてるような印象が強いのはアカンと思うからです。
・もちろん、「あんまり興味もないし『移植医療の歴史』に関する書物なんて読む気ないわ〜〜」ってのは当然です。
・ですので、需要が少ないことは承知のうえです!( ˆoˆ )/
・だけど、いつかどこかで『移植医療』の歴史をパッと知りたいと考えた時に(そんな時あるのか?とか言わない言わない...笑)、簡単に書かれた資料ってあまりないんですよねぇ〜。
・だったら僕がってことで、ここに超簡単に記そうと思いましたm(_ _)m
(今後、追加修正していく可能性の高い記事になると思います。)
・それから歴史においてはですねぇ、やや表現がきつい部分もありますので、そういったところは歴史を歪ませない範囲で、優しい表現を用いながらお伝えしていこうと思います。
では語ります。
はじめに
・移植医療は、不全あるいは欠損した体の部位を、他者の臓器や組織で置き換える医療です。
・紀元前400年に、ワンちゃん(🐶)による鼻から耳にかけて欠損したヒトに、自家皮膚を移植したと記載された書物がある。また、その書物には金属の義足を移植した患者についての記載もあります。
近代の移植医療
・1668年:Job van Meenerenがオランダで、ワンチャン(🐶)からヒトに移植した症例が、異種移植ながら世界初の成功例として記録されています。
・1822年:BurgerがAutograftでの皮膚移植を実施しました。
・1881年:Allograftでお亡くなりになられた方より提供された組織の移植が活発となりました。
臓器の移植に関して
・1906年:フランスで豚さん(🐷)の腎臓を、1909年にはドイツで初めて霊長類の腎臓をヒトに移植した異種移植症例が報告されています.....ですがこれらはすべて生着する事はありませんでした(涙)。
・1926年:ラムちゃん(🐏)の腎臓をヒトに移植したが、残念なことに9日後に患者さんはお亡くなりになりました。
初めての腎移植に関して(2つの説があります)
・説その1:1950年、Lawlerが実施したお亡くなりになられたからの腎移植で9ヶ月間の生着という報告があります。
・説その2:1952年、Hamburgerらが交通事故でお亡くなりになられた女性から、その息子さんへの腎移植を行い息子さんへ腎移植を行い、22日間生着したという報告があります。
→いずれも世界初として紹介されています。(どっちがどうなんだろう?)
心臓移植に関して
・1967年:南アフリカ共和国ケープタウンのGroote Schur病院にて、Dr.Christiaan Barnardが実施した18歳の交通事故でお亡くなりになられた女性から提供された心臓を移植した症例が世界初となっています。
本格的な臓器移植の時代へ
・本格的な臓器移植は、脳死下での臓器提供が1980年代になり免疫抑制剤の発展とともに普及していきました。
・1991年:世界保健機構(WHO)で、臓器移植のガイドライン(Guiding Primciple)が制定され、多くの国で臓器移植に関する法律が制定されました。
日本では・・・
・わが国においても例外ではなく、1996年に臓器の移植に関する法律が国会で度重なる廃案の後にようやく制定され翌1997年に施行されました。これが臓器移植法です。
・その後、脳死下での臓器提供では本邦の本人直筆の意思表示の提示義務、15歳未満の意思表示が不可欠であることなどにより、他国に比べて極端に提供数が少ない状態となりました。
・さらに、渡航移植に関しても国際的な非難が高まっていることなどから、早期の法改正による正常化が求められ、2009年7月、改正臓器移植法が可決され2010年7月に施行されました。
移植医療に関する大きな出来事
★1912年、Alexis Carrel博士は血管吻合および血管と臓器の移植に関する研究で、ノーベル生理学・医学賞を受賞しました
・1954年、Joseph MurrayとJ. Hartwell Harrison はボストンのピーター・ベント・ブリガム病院(ブリガム・アンド・ウィメンズ病院の前身)にて、最初の腎移植に成功した。移植される腎臓は患者の一卵性双生児が提供した。他の何人かの外科医が後に続いた。1960年代、アザチオプリン等の免疫抑制剤の開発により、マレーは一卵性双生児以外の、無関係なドナーからの移植を可能としました。
★その後、Joseph Murrayは、「人間の病気治療に関する臓器および細胞移植の研究」により、1990年にエドワード・ドナル・トーマスと共にノーベル生理学・医学賞を受賞
まとめ(近々【その2】へ続きますm(_ _)m)
※なんとなくでOKですので、「あぁ、そんなふうに進歩してきてんねや〜」って感じてもらえたら幸いですm(_ _)m
※移植医療に関しては、一人ひとりが常に立ち止まって考える医療だと思っています。
※どんな考えも、平等に尊重される権利があります。【4つの権利】
※この医療に携わるものとしてブログを通してお伝えしたいことは、『無関心』から『関心』へのお手伝いです(お節介バンザーーーーイ!です 笑)。
・歴史つながりとしては、こちらの記事もおすすめです。
・親(家族)としての考え方として参考になる記事です。
レシピエント背景とQOL調査に関する原著論文をサクッと批判的吟味

こんにちは、ちびパパナースマンです。
さっそくですが、僕の看護師歴を簡単に下記に示します。
- 看護師歴:15年
- 認定レシピエント移植コーディネーター歴:5年以上(専従)
こんな感じで日々患者さんやご家族、施設や地域の医療・看護への貢献、なにより僕の家族のためにコツコツ頑張っています。
少し古い論文ですが、サクッと批判的吟味しました。
※なお、本格的な批判的吟味ではなく、あくまでサクサク〜〜ッとですのであしからずm(_ _)m
腎移植を受けたレシピエントの背景とQOLに関する調査【原著論文】
https://ci.nii.ac.jp/naid/120002307735
Yuko HAYASHI, Investigation of Quality of Life in Kidney Transplant Recipients
Bull Fac Health Sci, Okayama Univ Med Sch 12: 37-44, 2001
(Original article)
背景
・腎移植後レシピエントのQOL向上を目指した看護援助を検討するために、移植後の QOLに影響すると考えられる、移植を受けた理由やそのときの気持ち、ローカスオブコン トロールをとりあげた。
目的
・レシピエントの背景がQOLとどのように関係しているのかを明らかにする。
対象者
・研究の同意 を得た腎移植後のレシピエント 119名
データ分析
・データ解析には、統計パ ッケージHALBAU Ver4を用いて記述統計並びに推測統計を行った。
・QOLを構成する5因子 (社会 ・経済的な機能、家族の姓、情緒的な支え、身体の健康、安 らぎと幸福)について、移植を受けた理由および移植に臨んだときの気持ちの異なる群を比較検討するためにt検定を行った。
・特に移植の理由では、 「生活 をより充実させたい」と 「透析が嫌」 と回答した群を比較する。これは移植の理由が「生活に向けて前向きである」ことと、「単に透析が嫌であるという感情」の違いが、移植後のQOLに相違をもたらすかどうかを比較検討するためである。
・また、LOCがQOLの構成因子と相関関係があるかを検討するためにピアソン積率相関係数を求めて推定を行った。
・次に、移植を受けた理由や移植に臨んだときの気持ちと性別、年齢、学歴、就労状況、ドナー腎の関連を検討するためにx2検定を行った。
結果
・レシピエントは移植後に何らかの身体症状や合併症 が生じていても、81%の者が人生を肯定的に感じていた。
・そして生活を充実させたいとして移植を受けた者が、また、ローカスオブコントロールの内的統制傾向が強い者ほどQOLを高める傾向にあった。
考察
1.人生に対する感じ方について
腎移植後の生活は慢性腎不全患者にとって大いに満足できるものとなっていることが明らかにされた。
看護婦はレシピエントに起こりうる身体の問題と共に、生活上の問題について継続して意図的に関わっていくことが重要になるであろう。
2.QOLの構成因子と移植を受けた理由、移植に臨んだときの気持ちおよび LOCの関係について
「生活をより充実させたい」として移植を受けた者の方が、社会 ・経済的な機能や家族の絆において高い水準で有意差が認められたように,、そのようなレシピエントは家庭や社会の中で生活をより充実させる目標を持って生活ができていることが伺える。
3.LOCについて
AbbeyらがQOLと関係する社会心理学的変数の一つとしてLOCを取り上げ、自分自身による生活のコントロール感がQOLに肯定的に関係していることをモデルのなかで示している。
本研究においても同様に,内的統制傾向が強い者ほどQOLを高める傾向が示された。保健行動では内的統制の強い者ほど健康的な行動を自主的にとるといわれており、個々人の LOCを考慮して関わっていくことが大切であると思われる。
結論
・看護婦はQOLに影響を及ぼすレシピエントの背景を加味して、移植前から適切な看護援助を行う必要性が示唆された
(注) 原著で「看護婦」と表記されていますのでそのまま表現しております現在は「看護師」です。
批判的吟味
論文のPECO
P:腎移植後レシピエント
E:質問紙内的による内的コントロール群
C:質問紙内的による外的コントロール群
O:QOLの違い
Research Question
F:実現性→◯
I:科学的興味→◯
N:独自性→△
E:倫理性→△
R:切実な問題→◯
結果
・研究バイアス(選択・測定バイアス)がかかっている可能性があり
・実行バイアスがかかっている可能性あり→交絡因子の調整は?
統計解析は妥当性
・多変量解析による交絡因子の調整や分析が最低限必要であろう
結果と考察との論理的整合性
・実施した統計解析は検討の余地があるが、各統計解析に対する考察は統合性が取れている
・特に、p値から結果を言い切らず、示唆(可能性)の記載に留めていることに関しては→◯
まとめ
・いまだ看護の研究や学会などでは、「t検定で有意差があったので〇〇と言い切れます」というような発表を見聞きする。これは"過誤"の視点からも注意しなければならない。
・p値に有意差がみられてもそれだけで「差がある/ない」とは言い切れないこと
・最低限、「p値は、帰無仮説が正しいという前提において、それ以上、偏った検定統計量が得られる確率」を示している。それ以上でも以下でもない、ということを知る必要がある。
・そのうえで、p値だけでなく(看護界は異様にt検定とp値が大好き)、結果を95%信頼区間で示す選択肢も知らなければならない。
ではまた〜〜( ^_^)/....
※QOLの観点から考えると、子供の成長・発達への視点を持つことも欠かせません。
子供の月例差に関する記事も合わせてどうぞ。
看護師国家試験を終えたみなさんへ。今から本気で学びましょう!

こんにちは、ちびパパナースマンです。
さっそくですが、僕の看護師歴を簡単に下記に示します。
- 看護師歴:15年
- 認定レシピエント移植コーディネーター歴:5年以上(専従)
こんな感じで日々患者さんやご家族、施設や地域の医療・看護への貢献、なにより僕の家族のためにコツコツ頑張っています。
さて、このたび厚生労働省より2019年3月22日に第108回看護師国家試験合格発表がありましたね。
今年度の看護師国家試験合格率は89.3%だったようです。
国家試験を受けたみなさん、お疲れさまでした。
今回は、そんな看護師国家試験を終えたみなさんへ、今から本気で学びましょう!ってお話です。
看護師国家試験を終えた今だからこそ、本気で学ぼう!
理由
"ローリスクハイリターンの種蒔きになるから"です。この時期にしっかりと種蒔きし、コツコツ水やりを続けることで、近い将来自分にとって大きな収穫に繋がる可能性があがります。
「これだったらめっちゃ頑張れる」ってことに取り組むのが最善だと思うけど、それ以外でも例えば「興味あるけどなかなか勉強できなかったこと」でもいいかと思います。
ではなぜ「今」なのかという理由を3つあげます。
1.まずは、本質論になりますが「今」に集中することの大切さを自分の中に落とし込むことです。
ここは本質的な部分なので、この時期圧倒的に学べたみなさん一人ひとりが将来「これか!」って感じてください。その瞬間は必ず訪れますので。
ポジティブな瞬間だけでなく、悩んだり苦しくなった時にも、今に集中することの大切さや努力してきた受験勉強の上にさらに上積みしたという努力の経験が、あなた自身を守る盾になります。
2.次に、盾にもなれば強みにもなる可能性があります(根拠は僕(n=1)です 笑)。
大切なのは、1でも述べたように「今努力した」という経験値ですが、その学んだ事柄が将来大きな強みになる可能性があります。
その根拠ですが、僕も国試を終えてから初出勤までの期間に自分なりに学ぶ努力をしました。何を学んだかというと、大好きなサッカーについて追求しようかとも考えたんですが、「今学んでおかないと、興味はあるんだけどこの先自分から積極的に学ぶことはないだろうなぁ〜」って考えてた"移植医療"について学ぶことにしました。これが将来自分の武器になるとはその時は考えてなかったけど、いろいろな巡り合わせで今に繋がりました。
3.最後に、なぜこの期間なのか?についてです。
受験勉強頑張ったという努力の上に、間をあけずに努力の上積みをすることで、「もう無理ぃぃ〜〜!」って自分で勝手に思い込んでた努力のリミッターをぶち破る経験をしておくことが、今も将来もあなたにとって大切だからです。そうすることで、これからの努力の平均値や最高値が上がり、周囲より群を抜いた圧倒的で効率的な努力から結果を出せる確率が上がると思います。
こういった話をすると・・・
「これから先、これだけ長期な心身フリーな状態はないと思うので、ギリギリまで目一杯羽を伸ばすほうがいい」みたいな話も聞きます。先輩たちもそういうふうに労ってくれる人が多いですよね。
厳しい学生生活を過ごしてきたし、ギリギリまで目一杯羽を伸ばしたいっていう気持ちは僕もよ〜〜くわかります。(てか、ずっと羽伸ばし続けていたい...笑)
一方で、"これだけ長期な心身フリーな状態はなかなかない"って自分で理解してる今だからこそ、この時期は子どもの頃....とまではいかなくても、そこをイメージできるくらい、スポンジのように吸収できる時期だと思います。
なので、この時期の本気の学びは、これからの自分に対する大切な種蒔き期間になるでしょうし、自分自身の支えや逃げ場所、一時避難所の礎になる可能性が高いです。もちろん武器になる可能性も。
まとめ

ここから新年度を迎えるまで、旅行やらなんやら羽伸ばしたい気持ちは2-3日の旅行くらいで区切りをつけ、あとはひたすら今から本気で学びまくりましょう!
あと、規則正しい生活リズムも必須です。期待と不安のスタートは、健全な心身であるかどうかが鍵をにぎります。向ける矛先は、外部環境ではなく自分の中にあります。
じゃ、大切なことなのでもう一度言いますね。
『看護師国家試験を終えた今から、本気で学びましょう!』*(^o^)/*
ブランクなんて怖くない|潜在看護師の復職へむけた心構えと勉強方法|潜在看護師の復職応援団
看護師として、ぜひ読んでおいてほしい記事です。
読んでくれた方は今後の看護に活かしてくださいね。
コメントいただいたこちらのサイト(https://kangosaikou.com/)の記事(https://kangosaikou.com/latent-nurse-pc-skills)もご参照ください。
認定レシピエント移植コーディネーターになるには【簡単まとめ】

こんにちは、ちびパパナースマンです。
さっそくですが、この記事の信頼性を担保するものを簡単に下記に示します。
- 看護師歴:15年
- 認定レシピエント移植コーディネーター歴:5年以上(専従)
こんな感じで毎日精進していますので、それなりに信頼性はあるかなぁと思います。
今回は、『認定レシピエント移植コーディネーター』に興味を持ってくれたみなさんに、普段はあまり読む気になれない【認定制度の規則】ってのを、意味内容に歪みがない範囲で箇条書きでまとめたのでご覧ください。
なお、同じ系統の記事も合わせてご覧いただくと、よりイメージが深まると思います。
認定レシピエント移植コーディネーターになるには
レシピエント移植コーディネーター認定制度規則
1.総則
(目的)
・公正かつ透明性の高い認定を行う
・移植医療の安全かつ公平公正な遂行と発展普及をはかる
・国民の福祉に貢献する
(運用)
・認定レシピエント移植コーディネーター(以下,認定RTC)制度の運用は
→レシピエ ント移植コーディネーター認定合同委員会(以下,合同委員会)が行う
(運用内容)
・認定RTC制度の[認定]・[資格検討]・[教育]など
2.新規認定(1回/年)
(申請資格)
1.日本の医師免許もしくは看護師免許を有し5年以上の臨床経験が必要
2.日本移植学会を始めとする臓器移植に関連する学会ならびに研究会の会員として学術活動に参加
3.別に定める実績要件を満たしていること(詳細は日本移植学会のホームページ参照)
4.日本移植学会および関連する学会・研究会の学術集会に3回以上参加(日本移植学会学術集会1回以上参加)
5.日本看護協会または日本移植コーディネーター協議会の主催する研修を受講(計3 日間以上)
6.合同委員会が認定する別に定めるセミナー,講習会などを1回以上受講(5.を含めな い)
(受験申請)
・新規申請者は,別に定める細則(いくつかの申請書類)に則って合同委員会に申請する
(資格審査)
1.受験資格に関する書類審査は合同委員会が行う
2.合同委員会は,書類審査の結果を申請者に通知し,資格審査合格者には試験の期日および場所を通知する
(試験)
1.試験は筆答ならびに面接試験とする
2.試験問題の作成,試験の実施,合否判定は合同委員会が行う
(認定証交付)
・合同委員会の合否判定に基づき,合同委員会構成各学会・研究会の承認を経て合同委員会委員長 名ならびに日本移植学会理事長名で合格者に認定証を交付する
※ちなみに、当時の僕の職場では実績条件を満たせなかったので、看護部長にお願いして条件を満たしている病院で数ヶ月間研修させてもらいました(その間は職場より、研修施設近く(電車で1駅)のところにレオパレスを用意してもらいました。でも研修施設で寝泊まりが多かったです 笑)
参考まで
3.更新認定
(更新)
・5年毎の更新制とする
(更新申請資格)
1.5年間継続して日本移植学会を始めとする臓器移植に関連する学会ならびに研究会の会員として学術活動に参加していること
2.レシピエント移植コーディネーターとして専従もしくは専任であること(なお医師については専従であること)
3.レシピエント移植コーディネーターとして直近の5年間に別に定める実績と業績を有すること
4.日本移植学会および関連する学会・研究会の学術集会に3回以上参加(ただし日本移植学会学術集会に1回以上参加)
5.日本移植学会の研修・セミナー・講習会を受講
などなど・・・・
まとめ
・今回は、『認定レシピエント移植コーディネーターになるには』というテーマに沿って規則を簡単にまとめました。
・こういったもの類いは、見る気になれない文書形態がほとんどですよね(笑)
・僕自身が「もっと見やすくしてくれたらいいのになぁ」と思っていました。
・「それなら自分でまとめればいいやん」....てことで、今回は制度規則を意味内容に歪みがない範囲でまとめました。
・事あるごとに、同じ系統の記事や、今後もアップしていく予定の"移植コーディネーターに関する記事"とあわせて読んでいただければ、より深まると思います( ˆoˆ )/
最後に

★文中にあります『レシピエント移植コーディネーター問題集』は、筆記試験のためには必須かと思います(いわゆる赤本ですね)。
★また、医師・看護師の勉強本としても活用できます。
★認定希望者は購入検討の必要性があると思いますが、安くはないので病院図書館に置いてもらう作戦もありですね。
こちらの記事もおすすめですよ〜〜〜\(^o^)/
ではまた〜〜( ^_^)/....
【ナース必見】不足してるからこそ移植コーディネーターの未来は明るい

こんにちは、ちびパパナースマンです。
さっそくですが、この記事の信頼性を担保するものを下記に示しますね。
- 看護師歴:15年
- 認定レシピエント移植コーディネーター歴:5年以上(専従)
こんな感じで毎日精進しているので、それなりに信頼性はあるかと思います。
不足してるからこそ、移植コーディネーターの未来は明るい
- まず、移植医療領域では絶対に必要な業種だから
- 次に、移植医療はまだまだ発展途上にあるヒヨッコだから🐥
- そもそも、ぜんぜん足りてないから...\( ˆoˆ )/
周囲の声
・「再生医療が今以上に発展すると需要が減ると思うんだけど、本当に未来は明るいの?」というような思いを抱く方(ナース)が結構いるんじゃないかなと思います。
・これに対する僕の答えは・・
→「たしかに一理あるかもしれません。でもそこはほぼ気にしなくて大丈夫だと思いますよ」...です。
理由
・そもそもが、移植医療は再生医療のひとつだからです
・その根拠のひとつとして、僕も学会員である学会HPを下記に示しますね。
・「へぇ〜、こういう学会あるんや〜」くらいで思っていただけたらいいかと...。
では、どうやったら移植コーディネーターになれるのでしょうか?

(院内コーディネーターは、所属長より「あなたは院内コーディネーターね」と任命されれば名乗れます)
・「レシピエント移植コーディネーター」と「ドナーコーディネーター」に関しては、下記の記事をご参照ください。
将来をふまえると、『認定レシピエント移植コーディネーター』資格は必須!
認定資格がないとどうなるのか?(多くの今の現場が、その根拠になるでしょう)
- まず、上記の移植コーディネーターに関する記事でも述べてるけど、移植コーディネーターはほぼ看護師であるということ
- どういうことかと言うと、いわゆる時代遅れの我々看護界において、病院内では他のスタッフと同様の1看護師として扱われる可能性が高いということ
- 実際、看護協会認定の各分野の認定看護師においても、日本中の多くの施設で他のスタッフと同様の1看護師+余った時間で認定活動、みたいな扱いを受けてますよね
- 院内コーディネーターも、病棟勤務で夜勤もがっつり入りながら、移植外来の時間だけ外来看護につくとか・・・・
では、認定資格(認定レシピエント移植コーディネーター)を取得するとどう変わるのか?

☆専従または専任資格なので、現場に埋もれず専門性の高い仕事ができるようになります!
そうは言うものの、再生医療が確立されれば終わりなんじゃないの?
- これに関しては、再生医療には僕たちのようなスペシャリストがいないこと。
- 上記でも述べたようにそもそも移植医療は再生医療のひとつであること。
- これらの理由から近い将来、認定レシピエント移植コーディネーターがさらに臨床や研究での学びを深めつつ、その役割を担っていく可能性が高いと考えます(私見です)。
- 仮に、新たな制度が作られても我々がその専門性では最も経験値が高い存在だからです。
少し過去の話を遡ると、
※現在、認定レシピエント移植コーディネーター資格は5学会認定の資格です。ですが本来は、高度な倫理観を要する仕事なので専門看護師(院卒)が妥当と言う議論がありました。しかしそうすとさらに、移植コーディネーターを目指す者が足りなくなることが理由のひとつとして現在の形になっています。

こういった話をすると
-
大変そう・・・・
-
もし途中で挫折したらと考えると行動に移せない
-
年齢ががが・・・・
よく聞くお話ですし、そう思うのも当然かなぁと思います(僕もそう思いました)。
ところが、実際はそうでもないんですよってことを示していきます
- 大変そう・・・はい、大変です(笑)。でも、あの看護師特有のドロドロした人間関係に比べればたぶん、最低でも40〜50倍くらいはマシな世界です
- 挫折しそう・・・これについても大丈夫です。なぜなら幸い僕たち看護師は、院内で配置転換の希望を出せますよね。晴れて希望通り転科できればそこで実績を積む。もしどうしても続けられない場合はまた移動すればいいんです。それが無理なら病院を変えればいいんです。経験したことは必ずその人の経験値アップに繋がりますからね。幸い我々看護師は、この資格がある限り、生活に困ることはないはずです。迷ってるなら、迷いながらでも明日希望を出してみてください
- 年齢ががが・・・それも全く問題ありません。その根拠は僕です(笑)。僕は25歳から5年コースで准看→看護師となり、認定RTCになったのが40才でした。余裕です😊
まとめ
※患者さんやご家族のことを考えると、移植医療から再生医療へ繋がっていくのはとってもとっても喜ばしいことですよね。
※近い将来その日が来るのを夢見ながら、今は目の前の患者さんと全力で向き合い続けることが大切であり、その積み重ねが未来へ繋がっていくことは、ほぼ間違いないと思います。
潜在看護師の方への広報・啓蒙・研修などを構築し、不足している移植コーディネーターへ興味・関心をもってもらうことは1つの施策ではないかと考えます。
関連サイト:潜在看護師の復職応援団
そもそも、2025年問題に伴う看護師不足が深刻化しています。
復職・転職をお考えの方に役立つ記事3選です。
正しい転職求人サイトの選び方・まとめ・おすすめランキングはこちら
腎臓移植にかかる費用の内訳 その2【いま!知っておくべきこと】
こんにちは、ちびパパナースマンです。
さっそくですが、この記事の信頼性を担保するものを下記に示しますね。
- 看護師歴:15年
- 認定レシピエント移植コーディネーター歴:5年以上(専従)
こんな感じで毎日精進しているので、それなりに信頼性はあるかと思います。
では、腎臓移植を例にしてどのくらいの費用がかかるのかを説明していきます(その2)
昨日記事にした(その1)も合わせてご覧くださいm(_ _)m
・国による違いや各臓器、方法によって違いがあること予めご了承くださいm(_ _)m
臓器移植には実際のところどのくらい費用がかかるのか(その2)
なぜ知りたいのか?
- 実際に腎移植が差し迫っている人にはめちゃくちゃ大切で需要ある内容であること。
- もし自分やご家族に移植が必要になった時を想像すると、やっぱり現実的に費用はどのくらいかかるのか?...とても不安で知っておきたいことだ思うからです。
- 保険適用なのか?
- 自己負担額は?
- 医療費の助成制度はあるのか?
- 助成制度の種類や自己負担額は?
※今回は、これらの疑問について腎臓移植を例に2記事に分けて詳しくお答えします
(1記事に詰め込むと、読者のみなさんも、僕も疲れるからです 笑)
医療費助成制度

腎移植に関する「医療費助成制度」にはどのようなものがあるの?
- 国の制度→自立支援医療(更生医療、育成医療)
- 地方自治体制度→重症心身障害者医療費助成制度、乳幼児医療費助成制度
自立支援医療(更生医療・育成医療)ってどんなの?
- 更生医療→18才以上、身体障害者手帳(腎機能障害)を取得、指定医療機関で腎移植を行う時にかかる費用の助成(保険適用分)
- 育成医療→18才未満、指定医療機関で腎移植を行う時にかかる費用の助成(保険適用分)
なお、自立支援医療は事前申請が原則となるのでここは注意が必要です(生体・献腎移植で申請のタイミングが異なります)
特定疾病療養受領証ってどんなの?
- 自己負担限度額:1000円/月
- 70才未満で高所得者(収入が600万円以上/年、53万円以上/月)は、 20000円/月
重症心身障害者医療費助成制度ってどんなの?
- 各自治体により内容が異なります
- 慢性腎不全、重度の腎機能障がある人に交付されます
- 保険適用分の全額または一部が助成されます
腎移植後の障害年金について
- すでに受給してる人は現況届を毎年提出の必要があります
- また、おおよそ3年に1度、障害の程度を確認するための現況届として、診断書提出の必要があります
- 診断書提出の際、移植後の経過が良好との判断があれば、支給停止または減額されます
- 移植後、1年間は支給停止や減額はありません
まとめ
- 今回は、2記事に分けて腎臓移植を例にあげて移植にかかる費用についてお話しました
- なかなかややこしい内容やし、漢字ばっかりで疲れる記事だったかと思います
- 最後まで読んでくれたみなさん、ありがとうございますm(_ _)m
- また暇な時にでもちょくちょくのぞいてご自身の中に落とし込んでいただければ幸いです
では、お疲れさまでした〜〜( ^_^)/....
腎臓移植にかかる費用の内訳 その1【いま!知っておくべきこと】
こんにちは、ちびパパナースマンです。
このブログから、みなさんが正確な移植医療の情報を知ったうえで、少しでも日常の話題にあがれば……そんな思いでいっぱいです。
- このブログで述べる管理人の意見はあくまで個人としての私見です。所属するいかなる団体の立場も代表するものではありません。
- また認定資格の条件・役割より、臓器移植に関して"常に中立の立場"であること予めご理解ご了承いただきたく存じます。
今回は、腎臓移植を例にしてどのくらいの費用がかかるのかを説明していきます
・各国による違いや、各臓器、移植の方法によって違いがあること予めご了承くださいm(_ _)m
臓器移植には実際のところどのくらい費用がかかるのか(その1)
みなさんの知りたいところだと思います。
なぜ知りたいのか?
- 実際に腎移植が差し迫っている人にはめちゃくちゃ大切で需要ある内容であること。
- もし自分やご家族に移植が必要になった時を想像すると、やっぱり現実的に費用はどのくらいかかるのか?...とても不安で知っておきたいことだ思うからです。
- 保険適用なのか?
- 自己負担額は?
- 医療費の助成制度はあるのか?
- 助成制度の種類や自己負担額は?
※今回は、これらの疑問について腎臓移植を例に2記事に分けて詳しくお答えします
(1記事に詰め込むと、読者のみなさんも、僕も疲れるからです 笑)
腎移植にかかる費用

腎移植にはどのくらい費用がかかるのか
- 腎移植には400万円程度の費用がかかります
- 血液型不適合の場合や抗ドナー抗体陽性の場合、プラス100万円
- 腎移植を施行した1年では600万円超、血液型不適合移植では700万円超
- 保険適用なので、所得に応じて1〜3割負担になります
- 特定疾病療養受領証や重症心身障害者医療費助成制度、自立支援医療を使うことで、自己負担額は0~2万円になります
血液透析と腎移植の医療費の差は?
- 血液透析では、年間約500万円の医療費がかかります
- 腎移植では、手術をした1年は600万円かかります
- 腎移植では、移植後の外来通院で約120万円になります
- 移植後3年目で、血液透析を続けてるより移植の方が医療費総額が少なくなります
献腎移植希望における登録費用
献腎移植希望登録にかかる費用
- 日本臓器移植ネットワークへの初期登録費用に3万円かかります
- 更新料として、年間5000円かかります
- 市区町村によっては、初期登録費用が補助になる場合があります
生体腎移植ドナーにかかる費用
ドナーにかかる費用
- 基本的には、ドナー(候補者)にかかる費用はレシピエント(候補者)の保険に組み込まれます
- 移植後の外来通院や、再入院が必要となった際の治療費は、生体腎ドナー本人の健康保険支払い(1〜3割負担)になります
- 何らかの理由で腎移植に至らなかった場合は、それまでの検査費用はドナー(候補者)の自己負担になります
ここまで読んでくれたみなさん、ありがとうございますm(_ _)m
まとめ
臓器移植とお金に関する話って、おいおいって感じてる方へ・・・
たしかに「臓器移植」「費用」ってハッピーな話題ではないですよね...(^_^;)
ですが、以前記事にした『4つの権利』や『意思表示カード』などの記事含め、今回のテーマもいわゆる「第二領域」=「緊急ではないが重要なこと」にモロ当て嵌まることです
こういったっことは、なかなか自分から調べることも少ないでしょう
しかし、”いつかその日が来たら”じゃなく『いま!知っておくこと』が大切です
では、下記に貼っております「その2」と、「第二領域」の最もたるお話も合わせてお読みくださいm(_ _)m
現代の臓器移植の課題と、異種移植の可能性

今回は、2019年3月4日にオンライン公開されたばかりの、ほやほやの論文をサクッと紹介します。
論文紹介に関する私の見解をaboutページに載せていますのでご参照ください。
(プロフィールをクリックで表示されます^ ^)
●臓器移植の歴史を示しながら、現代の移植医療の課題を示した報告です。
背景
- 臓器移植は現代医学において最も進歩した医療の一つであり、末期疾患の患者にとって移植医療は生存の唯一の機会を提供する。
- 臓器移植の歴史は、医療のあらゆる面に影響を及ぼしながら進歩している。
歴史
- 臓器移植の研究がより体系的になり、より文書化されるようになったのは19世紀の終わり頃である。最初の動物モデルはこの時代に開発されました。
- さらに20世紀初頭、フランスの外科医Alexis Carrel(後に米国に移住)が血管吻合のための新しい方法を開発した。
- 1912年、Alexis Carrel博士は血管吻合および血管と臓器の移植に関する研究で、ノーベル生理学・医学賞を受賞した。
- 最初のヒトからヒトへの移植は、1933年にウクライナの外科医UU Voronoyによってソビエト連邦で行われた。
課題
- 臓器移植の分野には多くの課題が残っている。
- 主な課題は、臓器需要と臓器利用可能性間の不均衡である。
- この問題を克服するためには、拡張基準移植片(ECD)を用いた移植、心臓死後の移植(DCD)などがあげられる。
- その他の課題には、周術期の患者ケア、移植片の生存、および免疫抑制プロトコルの最適化があげられる。これらの分野でいくつかの進行中の研究があります。
- 個々の臓器の移植に関連した具体的な課題がある。
結論
- これらの課題に対し、以前から存在する異種移植によって臓器保存に関連する多くの問題の解決策になるかもしれないと関心が高まってきている。
- しかし異種移植には多くの未解決の生理学的、微生物学的、および免疫学的問題が残っている。
- 異種移植は日本ではまだまだマイナーですが、移植学会では必ずセッションが設けられており、活発な議論がなされています。
- 異種移植は、臓器移植先進国においても報告にもあるように問題・課題が山積みです。
- 今後のこの領域における進歩と倫理を見守っていく必要があります。
下記に、原著論文の批判的吟味をしたブログも貼っておきますので、ご一緒にどうぞm(_ _)m
移植コーディネーターは最低限、2種類必要である
こんにちは、ちびパパナースマンです。
このブログから、みなさんが正確な移植医療の情報を知ったうえで、少しでも日常の話題にあがれば…そんな思いでいっぱいです。
- このブログで述べる管理人の意見はあくまで個人としての私見です。所属するいかなる団体の立場も代表するものではありません。
- また認定資格の条件・役割より、臓器移植に関して"常に中立の立場"であること予めご理解ご了承いただきたく存じます。
たぶん、「移植コーディネーター」と聞いたら、脳死を宣告された家族のもとに病院の暗闇から現れて、悲しむ時間も与えられないまま臓器移植の話を始める、超怪しい卑劣な感じの奴ってイメージを持つ人も多いんじゃないかと思います...(ちょっと誇張しすぎですかね 笑)。
今回は、移植コーディネーターは最低限、2種類必要なんですよっていうお話をします。
2種類の移植コーディネーターが必要な理由

理由は簡単で、臓器移植医療は、臓器を提供する側「ドナー」と提供を受ける側「レシピエント」という異なる立場がつながることで成り立っている医療だからです。
どちらの移植コーディネーターもほとんどが、自らその道を歩みたいと決めた看護師(医師も少々)が担当しています(ファイト--!)
具体的な仕事内容の違いは?
ざっくりと概要だけお伝えしますね。
少しイメージ掴んでもらえたら充分です。
・ドナー移植コーディネーター
ドナーコーディネーターは、ドナーからの臓器提供の調整や臓器移植に関する啓蒙活動を行う役割を担っており、社団法人「日本臓器移植ネットワーク」に所属する約20名と、同ネットワークから委託された都道府県コーディネーター約50名からなっています。
先ほど書いたドラマに出てくるような役割を担います。ただし、実際はドラマのイメージより100倍人に優しく、1000倍患者とご家族に寄り添う存在です^ ^
※ 近い将来、認定資格設置の方向で進んでいます
・レシピエント移植コーディネーター
・レシピエント移植コーディネーターは、移植の全過程で関わります。
・移植前のレシピエントやその家族への移植についての説明や、情報提供、移植に関する相談、登録の手配などを行います。
・精神的・身体的にも不安の多い待機期間中の体調管理や、移植準備への支援をしています。そして移植が決定したら、移植手術時の各種手配などを行います。
・ 移植後(退院後)はレシピエント、ドナー、ご家族の担当看護師およびレシピエント移植コーディネーターとして専従(専任)で、外来担当・検査入院などの調整・健康・生活指導などを行います。
・チーム医療に関わる多くのスタッフの調整役として、患者さんと接する機会が多く、患者さんや家族の気持ちが分かる看護師が、主にその役割を担っています。
※レシピエント移植コーディネーターには認定資格もあります【認定RTCと略します】(まあまあ厳しい条件をクリアすること、5年毎更新なのでその間まったくサボれないくらいのこれまた厳しめの条件をクリアしなければいけません。涙)
中立の立場と言っても・・・
・中立の立場って言っても、この仕事選んでる人ってやっぱり"臓器移植賛成派"とかじゃないとできないんじゃないか?というような質問を患者さんやチームスタッフから言われることがあります。
→これに関してはそう思うのも無理ないと思います。なにせ特殊性が強いですからね。
でもそんなことはありません。どんな仕事でも同じですが、”プロ”としてお仕事しますので個人の思想みたいなものは自宅に置いていきます。
・実際に移植コーディネーター同士での会話でも、臓器提供に対する思いは「それぞれ」なんですよ。少し深く言うと、「それぞれ」こそが臓器移植においては超重要な意味を成すんです。
このあたりのお話は、前回記事にした、【超重要】移植医療の4つの権利で述べてますのでよろしければご覧ください。
まとめ
・移植コーディネーターは最低限、2種類必要である
・ドナーコーディネーターと、レシピエント移植コーディネーターに分かれる
・暗いお仕事ではない(笑)
ではまた〜〜( ^_^)/....
【超重要】移植医療の4つの権利

こんにちは、ちびパパナースマンです。
このブログから、みなさんが正確な移植医療の情報を知ったうえで、少しでも日常の話題にあがれば……そんな思いでいっぱいです。
- このブログで述べる管理人の意見はあくまで個人としての私見です。所属するいかなる団体の立場も代表するものではありません。
- また認定資格の条件・役割より、臓器移植に関して"常に中立の立場"であること予めご理解ご了承いただきたく存じます。
今回は、タイトルの通り『4つの権利』は超重要ですよってお話です。
では、掘り下げていきますね。
データが示す現状
意志表示カードや移植医療って言葉は知ってる(聞いたことある)けれど、実際はあまり深く考えたり話し合ったりしていないという方が多いと思います...いや多いです。
上記の根拠は前回の記事を参照ください。
その理由としては、
・今のところ、自分ごとじゃないしなぁ〜
・話し合うって言っても、なんかよくわからへんし・・・
・なんか怖い
・・・・・・・・
・・・・・・・・
数え上げればキリがないですよね(^_^;)
移植に関する『4つの権利』
-
今回は、しつこいくらい『4つの権利』というワードを使います
-
なぜなら、いまここで『4つの権利』を知っておくことが超重要だからです
4つの権利
- 臓器を「あげたい」
- 臓器を「あげたくない」
- 臓器を「もらいたい」
- 臓器を「もらいたくない」
そしてこれらはどの考え方も尊重されなければいけません。
この中で、臓器を「あげたい」という人から、「もらいたい」という人につなげることが「いのちのバトンを繋ぐ」=「臓器移植」です。
逆に、「あげたくない」人と「もらいたくない」人の意思も同様の権利として尊重されます。この権利を守ることも移植医療者の重要な役目です。
提供や移植について説得したり強要したりすることは誰にもできません。
なぜ今なの?
ではなぜ、この『4つの権利』をいま知っておくことが超重要かと言いますと、"実際に自分や家族(親戚)に移植が現実のものとして迫ってきた時≒あなたも家族もほぼ冷静な判断ができない時"に、「家族や親戚からの圧力を感じている」や、「断ることはいけないことなんじゃないかと思ってしまう(思わされる)」ことがあるからです。
少し話がそれますが、僕たちレシピエント移植コーディネーターの役割(業務)のひとつに「移植相談」があります。
僕たちは移植医療の最初の窓口となります。
ざっくりな表現になりますが、『初回診察前〜初回受診〜周術期〜移植後』に至るまでずっと一番そばに寄り添い続ける存在です。
これ以上この話を続けると今回の主旨から離れてしまうので、ここだけおさえて続きを読んでください。
(移植コーディネーターの種類や役割の詳細に関しては、今後のブログでお伝えしていきますね)
そんな僕たちが臨床で向き合う症例の中での一例をお伝えします。
「主人の腎不全治療で生体腎移植を選択しました。でも本心は、子どもたちにもしものことがあった時のために私(妻)の腎臓は残しておいてやりたいんです.....でも義母や主人の親戚からの圧力を感じて今日まで過ごしました。それにこの本心がいけないことなんじゃないかと思う自分もいるので誰にも言えませんでした」
(プライバシー考慮し、内容は変わらない範囲で言葉や表現は一部変更しています)
このお話に対する僕の解釈は控えます。
みなさんがそれぞれの思いで何かを感じとっていただければと考えます.....。
まとめ
-
老若男女問わず、あなたには『4つの権利』があるんだということをどうか覚えておいてください。お願いしますm(_ _)m
-
いつかどこかで臓器移植の話題があがればその時は、お子さんやご家族・ご親戚、お友達へもこの『4つの権利』をぜひお伝えくださいm(_ _)m
お子さまの食事バランスや食物アレルギーに関するおすすめ記事です。
こどもフルーツ青汁の効果を解説!野菜不足の食物アレルギーっ子より | 家族リフティング
ではまた〜〜( ^_^)/.....
ヘルシーワークプレイス|7つの要因【業務上の危険と対策】|潜在看護師の復職応援団
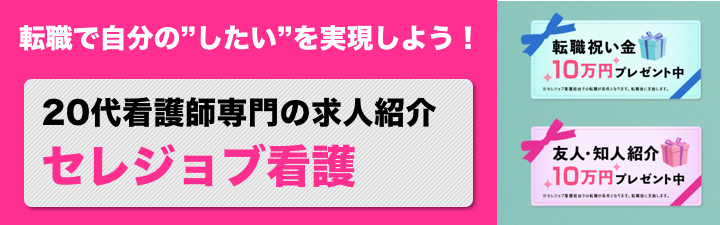
![みんなの医療統計 12日間で基礎理論とEZRを完全マスター! (KS医学・薬学専門書) [ 新谷 歩 ] みんなの医療統計 12日間で基礎理論とEZRを完全マスター! (KS医学・薬学専門書) [ 新谷 歩 ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/3148/9784061563148.jpg?_ex=128x128)